「英検2級に挑戦したいけれど、一体何問正解すれば合格できるのだろう?」 「知恵袋を見ても、人によって言うことが違ってよく分からない…」
このように、英検2級の合格ラインについて、はっきりとした答えが見つからずに悩んでいませんか。
この記事では、英検2級で一体何問ある問題のうち、何問正解で合格できるのか、2024年から始まる新形式の最新情報も踏まえながら詳しく解説します。
正答率6割で合格できるという話の真相や、複雑な英検2級のスコアの出し方、リーディングやリスニングで何問正解で合格を目指すべきか、といった具体的な疑問にお答えします。
さらに、何ミスまでなら合格可能なのか、実際のギリギリ合格の例はどうなっているのか、そして合格の裏ワザとも言えるライティングでの逆転術まで、あなたの知りたい情報を網羅しています。
この記事を最後まで読めば、漠然とした不安が解消され、合格に向けた明確な道筋が見えるので、ぜひ参考にして下さい。
- 英検2級の合否を決めるCSEスコアと合格基準点の関係
- リーディング・リスニング・ライティング別の具体的な目標正答数
- 多くの合格者が実践している効果的な学習戦略と時間配分
- 知恵袋で見られる合格ラインに関する疑問や不安への明確な回答
目次
英検2級は何問正解で合格?知恵袋の疑問を徹底解説
- 英検2級の試験で問題は全部で何問ある?
- 英検2級の合格に必要なスコアの出し方
- 2024年度版で何問正解で合格できるのか
- 結局、何問あってれば合格ラインなの?
- 合格には正答率6割が目安って本当?
- 知恵袋で見るギリギリ合格の例とは
英検2級の試験で問題は全部で何問ある?

英検2級の合格を目指す上で、まずは試験全体の構造を把握することが大切です。試験は大きく分けて筆記(リーディング・ライティング)とリスニングのセクションで構成されており、それぞれ問題数が定められています。
具体的には、以下の表の通りです。
| 技能 | セクション | 大問 | 問題数 |
|---|---|---|---|
| 筆記 | リーディング | 大問1 | 短文の語句空所補充 |
| 大問2 | 長文の語句空所補充 | ||
| 大問3 | 長文の内容一致選択 | ||
| ライティング | 大問4 | Eメール問題 | |
| 大問5 | 要約問題 | ||
| 合計 | |||
| リスニング | リスニング | 第1部 | 会話の内容一致選択 |
| 第2部 | 物語の内容一致選択 | ||
| 合計 |
このように、リーディングセクションは3つの大問で合計31問、ライティングセクションは2024年度から形式が変更され、Eメール問題と要約問題の合計2問が出題されます。そして、リスニングセクションは2つのパートで合計30問という構成です。
これらの問題数を知っておくことは、学習計画を立てる上での第一歩となります。どのパートにどれだけの問題が配分されているかを理解し、時間配分や対策の優先順位を考える際の基礎情報として活用してください。
英検2級の合格に必要なスコアの出し方

英検2級の合否は、「何問正解したか」という単純な素点の合計では決まりません。合否の判定には、「英検CSEスコア」という独自の指標が用いられます。これを理解することが、合格戦略を立てる上で不可欠です。
英検CSEスコアとは?
英検CSEスコアは、国際的な言語能力の指標であるCEFR(セファール)に対応した、ユニバーサルなスコア尺度です。このスコアの導入により、毎回難易度が微妙に異なる試験であっても、受験者の英語力を公平に評価できるようになりました。
リーディング、リスニング、ライティングの3技能に、それぞれ650点が満点として均等に割り振られています。つまり、満点は1950点(650点×3技能)となります。そして、英検2級の合格基準スコアは、このうち1520点と定められています。
素点とCSEスコアの関係
ここで最も注意すべき点は、素点(正解した問題数)とCSEスコアが単純な比例関係にはないということです。「1問正解すればCSEスコアが〇点上がる」といった簡単な計算はできません。
CSEスコアは、全受験者の解答データを用いた統計的な処理によって算出されます。そのため、多くの受験生が正解した問題のスコアは低く、逆に正答率が低かった難しい問題のスコアは高く算出される傾向があります。
この仕組みのため、自己採点の段階で正確なCSEスコアを予測することは困難です。これが、受験者が「あと何問で合格だったのか」を正確に知ることが難しい理由の一つとなっています。したがって、「1問の重み」は常に変動すると考え、どの問題も疎かにせず、確実に得点していく姿勢が求められます。
2024年度版で何問正解で合格できるのか

「結局、2024年度の試験では何問正解すれば合格できるの?」という疑問は、受験者にとって最も気になるところだと思います。
先に述べた通り、英検はCSEスコアで合否を判定するため、「何問正解すれば必ず合格」という明確なラインは公式に発表されていません。試験の難易度や全受験者の正答率によって、同じ素点でもCSEスコアは変動するためです。
しかし、これまでの多くの合格者のデータから、おおよその目安となる正答率は存在します。一般的に言われているのが、全体の約6割の正答が一つのボーダーラインになる、というものです。
例えば、リーディング(31問)とリスニング(30問)の合計61問で考えると、その6割である約36問の正解が目標となります。
ただし、これはライティングのスコアを考慮に入れていない計算です。ライティングは1問でCSEスコア650点満点のうちのかなりの部分を占めるため、ここで高得点を取れれば、リーディングやリスニングの多少の失点をカバーすることも可能です。
2024年度からライティングの形式が変更され、要約問題が加わりましたが、合格に求められる総合的な英語力のレベルや、6割程度が目安という基本的な考え方に大きな変更はないと考えられます。
結局、何問あってれば合格ラインなの?

「6割が目安と言われても、具体的な目標が立てにくい」と感じる方もいるかもしれません。CSEスコアの仕組み上、誰も「あと何問で合格」と断言することはできませんが、各技能で目標とすべき正答率を設定することで、学習のモチベーションを保ちやすくなります。
多くの合格者が提唱する一つの戦略は、以下の通りです。
- リーディングとリスニング: それぞれ6割程度の正答を目指す。
- ライティング: 満点を目指すつもりで対策し、8割以上のスコアを確保する。
なぜなら、リーディングとリスニングは問題数が多く、一つ一つの配点は相対的に低いと考えられます。一方で、ライティングはわずか2問(特に従来型の意見論述問題)で技能全体のスコアが決まるため、ここでの高得点が合格の鍵を握るからです。
全ての技能で満遍なく得点するのが理想ですが、現実的には得意・不得意があるはずです。もしリーディングが苦手であれば、その分ライティングで高得点を取ってカバーする、といった戦略的なアプローチが有効になります。
※ライティングで高得点を取得する方法については後述します。
要するに、合格ラインを「合計問題数の何問」と捉えるのではなく、「3技能の合計CSEスコア1520点」をどうやってクリアするか、という視点で考えることが大切です。
合格には正答率6割が目安って本当?

「正答率6割で合格」という目安は、多くの受験者にとって一つの指標となっており、これは概ね正しいと考えられます。
その理由は、英検が公表しているデータに基づいています。過去の試験結果を見ると、合格者の多くが全体の6割程度の素点を獲得しています。CSEスコアは統計的に算出されますが、結果として、3技能でバランスよく6割程度の正答ができていれば、合格基準スコアである1520点に到達する可能性が高いのです。
ただし、これには注意点もあります。あくまで「全体の目安」であり、「全ての技能で6割取れば合格」というわけではありません。
6割で合格できるケースとできないケース
例えば、リーディング、リスニング、ライティングの3技能すべてでちょうど6割ずつ得点した場合、合格基準に達する可能性は十分にあります。
一方で、極端に苦手な技能があると状況は変わります。仮にリスニングが満点で、リーディングが3割しか取れなかった場合、合計の正答率は6割を超えていても、リーディングのCSEスコアが極端に低くなり、合格基準に届かないという事態も起こり得ます。
逆に言えば、ライティングで8割以上の高得点を獲得できた場合、リーディングやリスニングの正答率が6割に満たない5割程度であっても、ライティングのスコアが全体を押し上げて合格するケースは頻繁に見られます。
これらのことから、6割という数字はあくまで平均的な目標とし、得意なライティングでスコアを稼ぐ戦略が有効であると言えます。
知恵袋で見るギリギリ合格の例とは

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトを見ると、「自己採点で55%だったのに合格しました!」「リーディングとリスニングは7割取れたのに、ライティングがダメで不合格でした」といった、さまざまな体験談が寄せられています。
これらの「ギリギリ合格」や「まさかの不合格」の例は、英検2級の合否判定の複雑さを物語っています。なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
主な理由は、やはりCSEスコアの仕組みと、特にライティングの採点にあります。自己採点では、リーディングとリスニングの素点は分かりますが、ライティングのスコアは全くの未知数です。
自分で「よく書けた」と思っても、採点基準(内容、構成、語彙、文法)に沿っていなければ点数は伸びませんし、逆に「自信がない」と思っていても、基本が押さえられていれば予想以上の高得点がつくことがあります。
知恵袋の例から学べることは二つあります。 一つは、自己採点の結果だけで一喜一憂しないことです。特に、リーディングやリスニングの出来が悪かったと感じても、ライティングで挽回できている可能性は十分にあります。最後まで諦めずに結果を待つことが大切です。
そしてもう一つは、やはりライティング対策の重要性です。リーディングやリスニングで安定して得点する力はもちろん必要ですが、合否を分ける最後の決定打となり得るのは、多くの場合ライティングです。これらの事例は、ライティングが単なるおまけではなく、合格のための最重要パートであることを示唆しています。
英検2級の合格へ!知恵袋でも話題のパート別対策法
- リーディングは何問正解で合格できる?
- 大問1は何問正解で合格を狙うべきか
- リスニングは何問正解が目標になる?
- 合格の裏ワザ!ライティングで逆転合格
- 英検2級は何問正解で合格?知恵袋の疑問を総まとめ
リーディングは何問正解で合格できる?
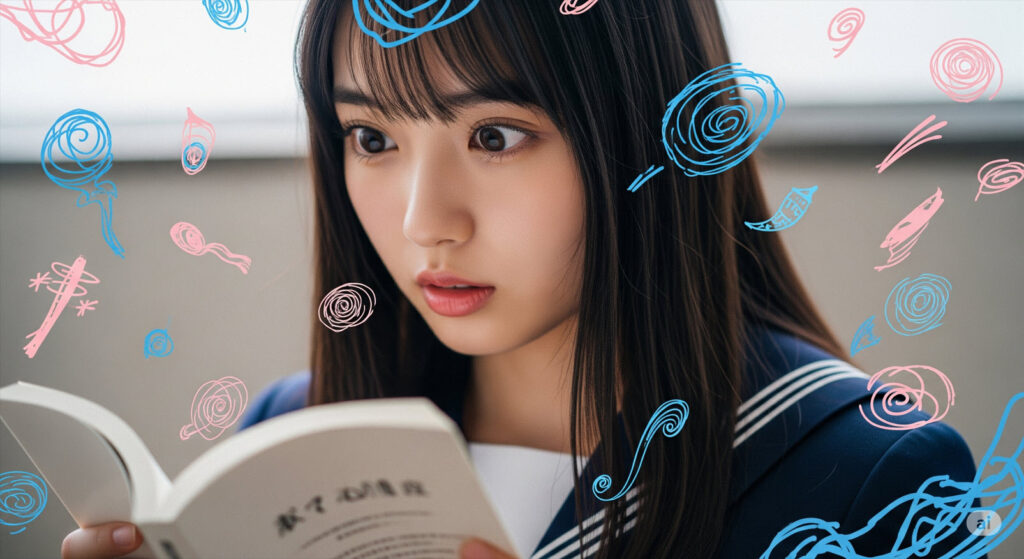
リーディングセクションは全31問で構成されており、合格のためにはここで安定した得点を確保することが求められます。明確な合格問題数は存在しませんが、目標としては6割程度の正答、つまり31問中18問前後の正解を目指すのが一つの目安となります。
リーディングは、語彙力を問う問題から長文読解まで、幅広い能力が試されるセクションです。時間内に全ての長文を読み解き、設問に答えるには、相応の速読力と精読力が必要になります。
特に、時間配分が合否を分ける大きな要因となります。大問1の語句空所補充問題は比較的短時間で解けるため、ここで時間を節約し、長文問題に十分な時間を割く戦略が有効です。
2024年度から形式が変更された大問3のEメール問題も、日常生活やビジネスシーンで使われる実践的な英語力が問われます。普段から様々な形式の英文に触れておくことが対策となります。
全てのパートで高得点を狙うのは理想ですが、まずは自分の得意な形式の問題で確実にスコアを稼ぎ、全体の6割を目指すという意識で取り組むと良いでしょう。
大問1は何問正解で合格を狙うべきか

リーディングセクションの中でも、特に大問1の「短文の語句空所補充問題」は、合格のための重要な得点源です。このパートは全17問で構成されており、リーディング全体の半分以上を占めます。
ここでの目標は、最低でも6割、つまり17問中10問以上の正解です。理想を言えば、7割(12問)以上を目指したいところです。
なぜなら、大問1は純粋な語彙力(単語・熟語・文法)が問われるパートであり、長文を読む必要がないため、知識さえあれば1問あたり数十秒で解答できるからです。ここで時間をかけずに高得点を確保できれば、精神的な余裕が生まれ、その後の長文問題にも集中して取り組むことができます。
逆に、大問1で時間を使いすぎたり、正答率が低かったりすると、リーディングセクション全体が崩れてしまう危険性があります。
これを達成するためには、地道な単語学習が欠かせません。市販の単語帳を1冊完璧に仕上げることを目標に、毎日コツコツと学習を続けることが、大問1の攻略、ひいては英検2級合格への最も確実な道筋となります。
大問1の攻略に関しては、「英単語を1日で300個覚える秘密の暗記術とは、最速で語彙を増やす秘密の方法を遂に公開!」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にして下さい。
リスニングは何問正解が目標になる?

リスニングセクションは全30問で構成されており、リーディングと同様にCSEスコア650点が割り振られています。ここでの目標も、やはり6割、すなわち30問中18問程度の正解が一つの目安となります。
リスニングは、一度対策のコツを掴むとスコアが安定しやすいパートです。放送は一度しか流れないため集中力が必要ですが、出題形式はある程度決まっているため、慣れが大きく影響します。
最も効果的な学習法は、過去問を繰り返し解くことです。ただ問題を解いて答え合わせをするだけでなく、以下のステップを踏むことが実力向上に繋がります。
- まずは普通に問題を解く。
- 間違えた問題や自信がなかった問題のスクリプト(放送文)を確認する。
- スクリプトを見ながら、音声に合わせてシャドーイング(影のようについていく音読)を行う。
- 音声を聞きながら、聞き取った単語を書き出すディクテーションを行う。
これらのトレーニングを繰り返すことで、英語の音声に耳が慣れ、聞き取れる単語やフレーズが増えていきます。また、設問が読まれる前に選択肢に目を通し、話の内容を予測する「先読み」のスキルも、リスニングのスコアを上げる上で非常に有効なテクニックです。
英検2級の過去問は、無料で3回分が公開されていますし、問題のスクリプトもダウンロードできます。過去問は原点にして頂点の参考書なので、ぜひ何度も繰り返して、リスニングを攻略して下さい。
合格の裏ワザ!ライティングで逆転合格

英検2級の合否において、最大の鍵を握るのがライティングセクションです。わずか2問(従来型の意見論述と要約問題)で、リーディングやリスニングの技能全体と同じCSEスコア650点が配分されているため、ここはまさに「合格の裏ワザ」とも言える逆転可能なパートです。
リーディングやリスニングの出来が今ひとつでも、ライティングで高得点を獲得すれば、一気に合格ラインを越えることができます。目標は8割以上のスコアです。
高得点を取るためのポイントは、「英作文の型(テンプレート)」を身につけることです。特に意見論述問題では、以下の構成に沿って書くことで、論理的で分かりやすい文章を効率的に作成できます。
- 序論(Introduction): 自分の意見を明確に述べる。(I think that ~. / I agree with the idea that ~. など)
- 本論1(Body 1): 意見を支持する一つ目の理由と具体例を挙げる。(First, ~. For example, ~.)
- 本論2(Body 2): 意見を支持する二つ目の理由と具体例を挙げる。(Second, ~. In addition, ~.)
- 結論(Conclusion): 序論で述べた意見を、別の言葉で再度述べて締めくくる。(For these reasons, I believe that ~.)
この型に沿って書く練習を繰り返すことで、本番でも迷うことなく書き進められるようになります。難しい単語や複雑な構文を使う必要はありません。むしろ、簡単な言葉でも文法的なミスなく、自分の意見を明確に伝えることが高評価に繋がります。
英検2級ライティングのテンプレートに関しては、「英検2級のライティングで使える表現を知恵袋がテンプレートに総括」で詳しく説明していますので、ぜひ参考にして下さい。
英検2級は何問正解で合格?知恵袋の疑問を総まとめ
この記事では、英検2級の合格ラインに関する様々な疑問について解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
- 英検2級の合否は素点ではなくCSEスコアで決まる
- 合格基準スコアは3技能合計で1520点
- リーディング・リスニング・ライティングに各650点が配分される
- 「何問正解で合格」という明確な基準は公表されていない
- 全体の約6割の正答率が合格の目安と言われる
- 自己採点での正確な合否予測は難しい
- リーディングとリスニングは6割程度の正答を目指すのが理想
- リーディング大問1の語彙問題は特に重要で6割以上を目標にする
- リスニング対策は過去問のシャドーイングやディクテーションが効果的
- ライティングは合否を分ける最重要パート
- ライティングはテンプレート活用で高得点を狙える
- ライティングで高得点を取れればリーディングやリスニングの失点をカバーできる
- 知恵袋のギリギリ合格例はライティングの重要性を示唆している
- 2024年度からライティングに要約問題が追加された
- 事前の準備と戦略が英検2級合格の全てを決める
~ 関連記事 ~
・ 英検2級の難化傾向に高校生が苦しんでいる件とそのライティング対策について
・ 英単語を1日で300個覚える秘密の暗記術とは、最速で語彙を増やす秘密の方法を遂に公開!
・ 英検の二次試験対策、英語面接を突破するために必要な3つのシークレットとは?
・ 英検2級のライティングで使える表現を知恵袋がテンプレートに総括
・ 英検の過去問のやり方、使い方を徹底解説。世界一優れた教材、過去問の凄さとは?
・【英検S-CBTとは】コロナ禍が英検に与えた、オンライン化の変革とは・・・
・ 【英語脳の作り方】英語の成績が急上昇する中高生に見られる、ある特徴とは?
・ 英語の伸び悩みに苦しむ高校生のお子さん、親はどう接すればよいのか?
・ 【初公開】最強の暗記術、一瞬で確実に記憶する知られざる方法とは
・ 共通テスト対策の単語帳でおすすめを厳選、不可能を可能にする最強のアイテムとは?
・ 都城の高校生が留学すると、英語の成績が急上昇する、それは本当か?
・ 英語で苦手を克服するか、得意なことを伸ばすかは、永遠のテーマ
・ 英語SVOCの意味、最も理解しにくい文型の訳し方とは?
・ 【英検外伝】英検と旺文社の不思議な関係、なぜ英検に関する書籍のほとんどは旺文社なのか?







